第一章 運命の出会い


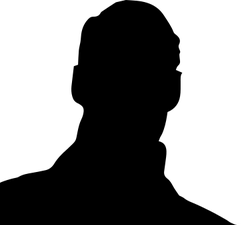
討伐し倒れたカトブレパスの前に立ち、誇らしげに言うマキシリオンとライダ。
派手な立ち回りによって装備は摩耗し、回復薬や閃光玉、トラップアイテムなどの消費は激しいが、そのぶんかなりのスピード感で討伐できた。
マヤの笛によるステータス強化や回復などが必要ないほどだ。
さすがはソウルヒートだと、マヤは素直に感心する。
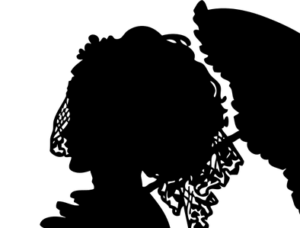

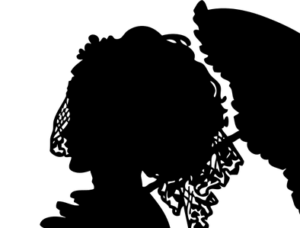

今回スノウの使っていた矢は、先端に麻痺や毒、麻酔などの効果がある液体が塗り込まれていた。
弓矢は近接武器に対して威力がないぶん、状態異常系の攻撃でサポートするのだ。
とはいえ、スノウの弓の腕はお世辞にも良いとは言えず、高価で貴重な矢をかなり無駄にしていた。
金欠にあえぐハンターなんかは、外しても再利用できそうな矢を回収していくが、スノウはそんな殊勝なことはしない。

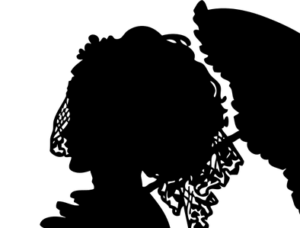

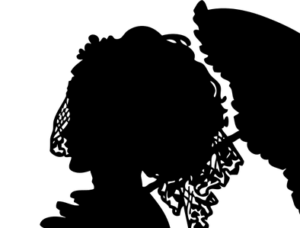

ため息混じりのあきれたような物言いに、マヤは絶句した。
金銭感覚を身に着けていないのは、いったいどちらだと。
実際のところ、スノウ程度の腕前の弓使いであれば、そこら中にいる。
それでも彼女が遠距離支援としての存在感を保てているのは、その高級な弓の威力と毎回大量に消費する矢のおかげだ。
そんなことにも彼女は気付いていない。
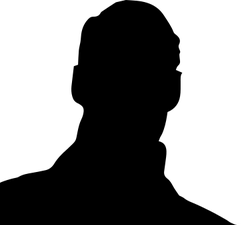
お? レア素材ゲット~!
カトブレパスの死骸から素材を剥ぎとっていたライダが上機嫌な声を上げる。
その手には、血にまみれているものの磨けば輝きそうな、丸く赤い半透明の球体が乗っていた。

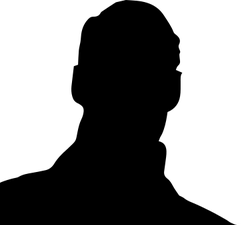

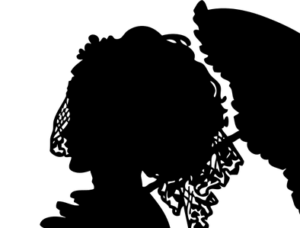

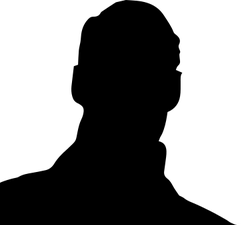
そう硬いこと言わないでくれよ。あれを作れば、もっと楽にクエストだって攻略できるようになるんだからさ
危機感を覚えたマヤが声を上げるが、ライダは聞く耳を持たず、マキシリオンとスノウは眉を寄せいらだちを見せていた。
いくら強いパーティーだからといって、金が無限に湧いて出るわけではない。
マヤはソウルヒートの大きな問題点に気付いていた。
彼らが強力な魔物を難なく討伐できるのは、多くのクエストをこなして手に入れた、希少な素材と大金を用いて強力な装備を作り、さらに劣化や損傷の修復などの維持費に大金をつぎ込んでいるからである。
さらに、敵の動きを止めるための閃光玉やトラップなどの消耗品から、大量の回復薬や体力増強剤などを毎回惜しげなく使い、クエストのたびに大量購入している。
明らかに、クエストをクリアして得る稼ぎよりも出費のほうが多い。
実際のところ、マキシリオンは鬼人族として凄まじい腕力を持っているし、ライダもかなり俊敏だが、それは高品質の装備による恩恵によって能力を底上げされているからだ。


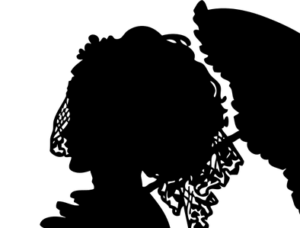

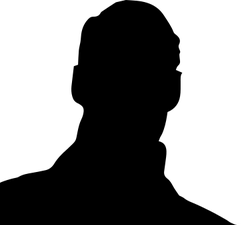
マヤの肩を持つようにライダは言って、流し目を向けてくる。
彼女はあきれて反論する気も起きない。
今はただ、どうすることもできず様子を見るしかないのだと、無理やり納得するのだった。
…………………………
ある日の早朝、ヤマトは見晴らしの良い丘で景色を眺めていた。
町のすぐ近くにあり、モンスターがいないため一般に開放されているスポットだ。
ヤマトが『トリニティスイーツ』の仲間となってから一週間が経った。
しかし、彼女たちの借金を肩代わりしたことも、資金管理を引き受けたことも一度だって後悔はしていない。
『――ヤマト、お金というのはね、誰かを救うために、幸せにするために使うものなんだよ』
ヤマトは幼い頃、一文無しで死にかけていたところを個人投資家に救われた。
その教えは今でも心に生きているのだ。
だから、ソウルヒートでどんなに酷い扱いをされても、しっかり資金管理をしていたのは、彼らの助けになるというその一心だった。
それが揺らいだとき、ヤマトはもう投資家ではいられなくなるのだから――


ヤマトは肩にとまったピー助に微笑む。
楽しいというのは本心だ。
今は、トリニティスイーツの資金効率を上げるために、アイテムの調合だったり費用を削減できる強化の手順だったりを指南していた。
以前のパーティーでは、彼の言うことは誰も聞かなかったが、ラミィもハンナももちろんシルフィも、素直で従順だからアドバイスの通りにやってくれる。
それだけ信用してもらえているというのは、なんだかおもはゆい。


パーティーの資金繰りをいくら改善したところで、個々の能力は並程度かそれ以下。
ソウルヒートも、マキシリオンが鬼人であること以外は似たようなものだったが、ラミィたちを彼らのような実力派パーティへ育てるには相当な時間がかかる。


どんなに強い魔物も、より強い装備により強力なアイテムを持っていたほうが、倒せる可能性は格段に上がるのだ。
個々の能力や経験の差など、大きくは影響しない。
とはいえ、その資金をどうやって得るかで頭を悩ませているのだが……



突然右肩でピー助が首を立て鳴き出した。
すると、東の方角からピー助に似た、水色の小鳥が飛んできた。


飛んできたのは、『ポゥ太』という水色の小鳥で、ピー助と同じくヤマトの友達だ。
よく色んな地域を飛び回っては、ヤマトの元へ戻り、世界情勢を伝えてくれる。
ポゥ太はヤマトの左肩にとまると、「クワァッ!」と元気良く鳴いた。



ポゥ太から詳しく聞いてみると、他国ではまずいことになっているようだった。
なんでも、資源国であるエルフの国『ヴァルファーム』で、疫病が蔓延しているらしい。
感染力と致死率が高く、町での商売や入国が制限されたりして、経済が停滞し始めたようだ。
そこでヤマトは、顎に手を当て何事かを考えると、頬を緩ませポゥ太へ微笑んだ。

