プロローグ

『ヤマト・スプライド』は、この町で最強パーティへと成り上がった『ソウルヒート』のリーダーからそう告げられていた。

場所はギルドのクエスト仲介所。
仲間たちの帰りを待っていたヤマトがかけられた言葉は、「ただいま」というありふれた言葉ではなかった。
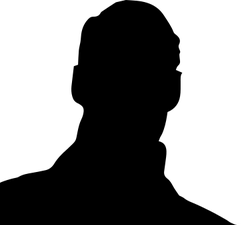

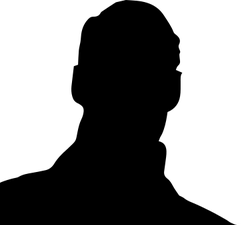

ヤマトは足手まといになるからとクエストには同行させてもらえず、彼らが戦っている間に次のクエストで必要になる消耗品の調達や割安な装備の調査、厳密な帳簿の作成と予算計画を立てていた。
これは決して雑用ではなく、ハンターパーティの運用における重要な役割だ。
そのおかげで、ソウルヒートは効率良くクエストをこなしていけているのだとヤマトは自負している。
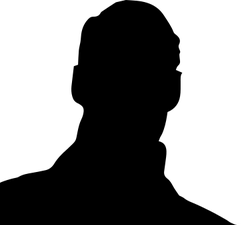

整った顔立ちの剣士『ライダ』の言葉に、ヤマトが反論すると、リーダー『マキシリオン』の横に立っていた、金髪ショートカットの女『スノウ』が口を開いた。
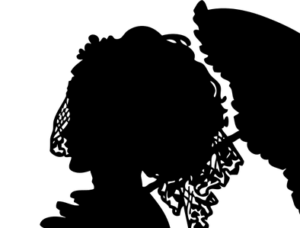

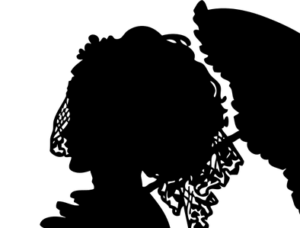

マキシリオンがゲラゲラと声を上げて笑い、ヤマトの顔が青ざめる。

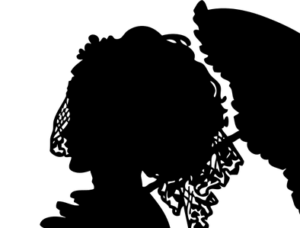
好きに使えたとは言うが、彼らの金使いが荒すぎてそんな簡単なことではない。
スノウの言葉に反応し、ヤマトの肩に乗っている白い小鳥が威嚇するように鳴いた。

ヤマトだけは小鳥の言っていることを理解していた。
実は、幼少期の生活の影響で、彼は鳥やリスなどの言葉が分かるのだ。
しかし粗暴な仲間たちには、耳障りな雑音にしか聞こえない。
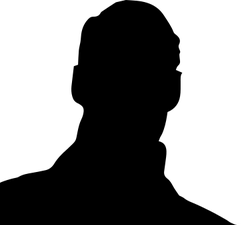
端正な眉を歪めたライダが剣の切っ先をヤマトへ向けると、小鳥は怯えて鳴き止む。
ヤマトが悔しさと怒りを滲ませて、リーダーのマキシリオンを睨むが、彼は薄ら笑いを浮かべて告げた。





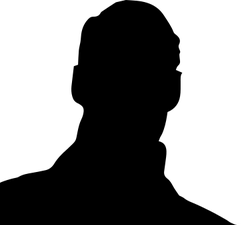
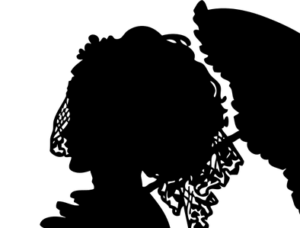
ヤマトは三人の見下すような視線を背に、ざわざわしている周囲のハンターたちの視線を浴びながら、去って行く。
仲介所の木製の扉を開けたところで、ライダが追い打ちとばかりに叫んだ。
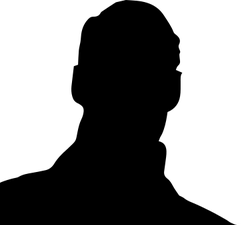

ヤマトは金も職も奪われ、どん底に落とされるのだった。
しかし、リーダーのマキシリオンも、ライダも、スノウも、誰一人気付いてはいない。
ソウルヒートがなぜ、あまたの高ランククエストを連続でクリアでき、最強にまで上り詰めることができたのかを――
…………………………
ヤマトを追い出したソウルヒートは、その日の夜、新たなメンバーを迎え入れた。
町で一番大きな料亭の中央で、豪勢な料理の並ぶテーブルを前に、戸惑いの表情を浮かべているマヤだ。
最強のパーティと名高いソウルヒートの人気は凄まじく、今も周囲の客たちが羨望の眼差しを向けている。
イケメン剣士のライダがファンサービスとばかりに、女の子たちへ微笑むと、黄色い声援が上がった。
ソウルヒートは、鬼人族で大剣使いのリーダー『マキシリオン』、俊敏に動きアイテム運用とアタッカーを両立する色男『ライダ』、貴族令嬢でありながらハンターをしている弓使いのスノウ、と噂通りの強者ぞろいで、マヤは期待に胸を膨らませていたのだが――
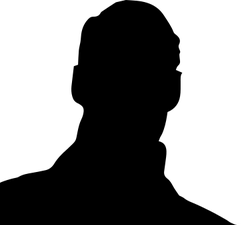
ライダが前髪をかき上げ、白い歯を見せて微笑む。
彼は少し長めの黒髪に、爽やかな容姿で女性からの人気が高いイケメンだが、マヤは彼のナルシスト感が好きになれなかった。
先ほども、艶のあるマヤの長い黒髪に触れてこようとして、ゾッとしたぐらいだ。

マヤは鼻筋の通った美しい顔を引きつらせ、淡々とした声で告げる。
それを緊張していると勘違いしたのか、マキシリオンが握った拳をマヤの胸の前へ突き出した。


マヤが両手でおわんの形を作ると、マキシリオンの手が開かれジャラジャラと少なくない額の通貨が渡された。


目を丸くするマヤに、マキシリオンはニヤリと片頬をつり上げる。
この席も彼女を歓迎するためにわざわざ予約したというし、ずらりと並んだ高級料理を見る限り、かなり羽振りがいいようだ。
マヤは不安を隠すことなく、いぶかしげに眉を寄せる。
以前いたハンターパーティも、それなりの実績はあったが資金面では苦労し、派手な出費は抑えていたのだ。

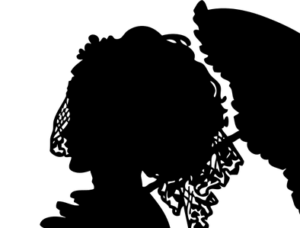

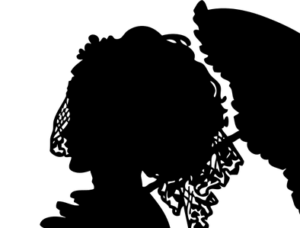


感情の起伏が少なかったマヤが、驚きを隠せず声をうわずらせる。
それもそのはずだ。
そこに記載されていた帳簿には、約2000万ウォルという、そこらの平凡なハンターでは何十年かかっても貯められない金額が書かれていたのだから。
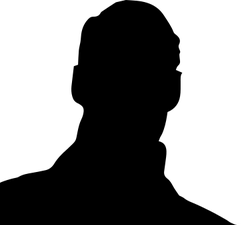
ちゃん付けにイラッときたマヤだったが、ホッと胸をなでおろした。
これだけの余剰資金があるのなら、手付け金やこの料理代など大したことはない。
それに、ハンターは強い装備や使用するアイテムが強さを大きく左右する。
つまり、それらを買うための資金力がハンターの強さのすべてだ。
先ほどから感じていた不安は杞憂だったと、マヤは頬を緩めた。

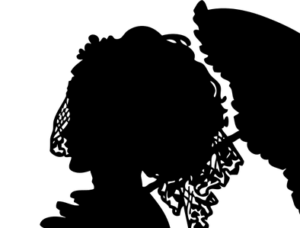

しかし、資金管理のすべてをヤマトに任せていた彼らは知るよしもなかった。
金庫番の預金口座に預けていたその資金の多くが、彼らの稼いだ金ではなかったことを――
